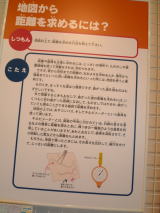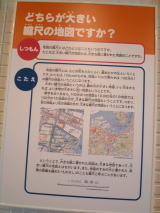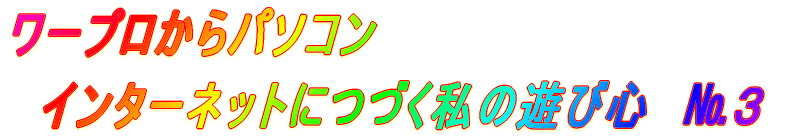| 「機関誌 海洋だより」に記載した稿を再編集して紹介しています |
ワープロからパソコン、インターネットに続く私の遊び心 №3
サーフメイズ JAPAN 事務局長 上瀧勇哲
皆さん、こんにちは、今度は社会人となり始めて勤めた吉田印刷株式会社のお話しをしたいと想います。その吉田印刷KKは北九州市若松区浜町にあり、会社の隣に洞海湾、その海をまたぐ当時、東洋一長いといわれた若戸大橋があり、私は毎日、北九州市小倉から若戸大橋を利用しながら通勤していました。その吉田印刷KKは若い社員が200人ほど働き、市内では指折りの会社で、二代目を継ぐ吉田正人社長は身長185㎝もある立派な体格を持ち、威圧感と優しさを合わせ持つ社長でした。その社長から「上瀧くん、君は職場を全部をまわってもらうよ」ということで、最初は平版印刷機械を学んでくれ、という事で、空閑敏明課長直属の部下になります。その空閑課長こそが私の釣り人生を芽生えさせた恩師でもありました。
当時は熊本市の大洋デパートのDMやチラシ、北九州市、官庁関係の書物が多く、毎月の残業が100時間を越えるぐらい大忙しの印刷所でした。その吉田印刷KKを隅々まで学び、経営学からつながる対外企業人と政治の結び付きを後日知る事になります。
入社当時は私と同等の若者が半数ほど居て、活気がみなぎっていました。その中で学生上りの私が釣りをするという事で、職場の先輩達から釣りに誘ってもらう事が増えてきます。当時18才で車の免許を持ち、19才でホンダN360(軽自動車)で通勤する若者は社長と専務ぐらいで、ましては営業マンでもないヤツが偉そうに車で通勤する事はマレでもありました。これには訳があり、小倉から若松の通勤が毎日1時間以上かかり、残業時間が毎月80~120時間もあった時代で、どうしてもバス通勤などができなかったのです。
そんなときに釣りキチの空閑課長から釣りに誘われ、宮崎県門川町いおん川港から出船する松田渡船で大ビロー島の石鯛釣りが始まりました。
磯釣り等したことのない私でしたが、上司から救命具や磯靴、竿、リールをタダで貰える事で、イヤイヤ磯釣りにハマる事になります。週末の土曜日夕方北九州市若松を出発して深夜2時、宮崎県門川町いおん川港着。仮眠して4時出船し、5時過ぎには大ビロー島に上磯。昼2時、納竿して、夕方5時には国道10号線を北九州市若松まで8時間から9時間の運転を私一人でします。深夜1時、2時の若松着が当たり前で、そのまま家に帰らず会社で泊まり、朝から仕事。そして毎日、深夜10時まで残業しながら5月、6月の磯釣りがありましたね。
上司と付き合いのある対外企業経営者と、お世話係を兼ねた釣りをイヤイヤする事が多くありましたが、その遊び心を空閑課長から学び、私の生き方をこの時代で確立したと想います。その先輩達がベースとなり立ち上げた吉田印刷磯釣倶楽部が25人ほどで結成され、無理やり押し付けられた会計で、社内の集金人となり、増々先輩達から釣りに誘われ、運転手 兼 小間使い人として存在感を高め、吉田正人社長から「魚釣りがそんなに楽しいかね」とイヤミを言われるぐらいになっていました。
趣味が釣りという事で、釣りクラブの会計 兼 書記という立場で会長をサポートしながら、20代の若者が企業人として学ぶ事で印刷業をプラスにするアクションがあり、先輩、上司が後押ししてくれる事で、なぜかしら社長、専務から可愛がられたよき時代でした。
24才で今の洋子ちゃんと社内恋愛して結婚するのですが、この恋愛時代でも吉田正人社長が「城戸武治 市議会議長さんとか麻生太郎 議員さんを前にして「上瀧くん、お二方が仲人してくれるので、話しをつけてやろうか?」のスピーチを大勢の新年会とか懇親会場で何度も言われて、ちょっと恥ずかしい良き想い出がありましたね。
その昭和時代は麻生太郎さんが北九州市若松区までが選挙区だったので、頻繁に吉田正人社長に会いに来ていました。吉田正人社長の身近なご親戚に吉田磯吉さんという国政を大きくリードした芦屋町出身の国会議員が居ました、その息子さんは当時の若松市長でもありました。そして麻生太郎さんのおじいさんは、あの有名な吉田 茂 総理でしたから、国政に関わる麻生さんと吉田家との繋がりは、ご両家で深い絆がありました。又、吉田正人社長は北九州若松ライオンズクラブの会長など歴任して、企業人はもとより政治と行政にも深く関わり、100万都市、北九州市の地域人として広く活躍された方です。その会社の社員である私は、まだそのような凄い社長だとは全く感じてない若者でもありました。その麻生太郎さんは現在、副総理 兼 財務大臣ですが、(公財)日本釣振興会の名誉会長でもあります。
その会社の中で私は平版印刷部門、製版部門、活版製版、機械部門、そして営業部にも回されていました。そのような若い時代、妻となる洋子ちゃんと北九州市若松区で10年間住み、二人の男女もうけました。その10年間は企業人として、あるいは釣り趣に於いても最も大切な礎を築くベースとなりました。
本文では釣趣を主に紹介していますが、まず吉田印刷磯釣倶楽部を解体して、一般釣り人が参加できる海洋磯釣倶楽部を昭和51年3月に結成しました。当時は16人でしたが、活性期には37人が登録された時代もあります。結成当時はコミュニケーションを主とした毎月の定期釣行会を重ねてゆきますが、近場の釣りから、ファミリーでも参加できる釣行会をしますから、大きな魚とか、たくさん釣る釣行会ではなく、参加形の釣りクラブでもありました。しかし昭和52年に九州磯釣連盟が発足され、全員参加した海洋磯釣倶楽部は一気にレベルアップさせたアクションプログラムがあります。本文では九州磯釣連盟との繋がりは小さく紹介しています。
海洋磯釣倶楽部初代の保里剛太郎会長は会社大先輩の印刷機械の課長さんで、県立若松高校ラグビー部のキャプテンをしていたほどの体格でしたが、趣味にした釣りが少々で、私と一緒に学ぶ方でしたから、保里会長が「ジョーさんが書記長(事務局長)になってくれ」という事で、二人で一人前の海洋磯釣倶楽部が誕生したのです。その保里会長の友人に、あの若松敬竿さん(月刊釣ファーン先代社長)は、若松高校の同級生でした。
海洋磯釣倶楽部のPRとかコミュニケーションの情報発信で、手書文を多く出している私でしたが、個人的な文章を活字文字にして印刷できるワープロという機器が、ベスト電器店で一台10数万円で始めて登場したのが昭和58年ごろです。1800年ごろから広くヨーロッパから日本で多用されていたタイプライターが、電算計数文字盤から文字がインクリボンへ熱転写され、紙に印刷できるワープロが、この頃より普及を始めたのです。その当時の10万円は地方公務員の賞与2回分で、30代になったばかりの私には、とっても手にできる品ではなかったのです。しかしワープロの活用方法を考えると、まだ会社に無いものを持ち、先駆けして営業とか社内情報発信活用に、いち早く貢献ができると想い、洋子ちゃんにお願いしてNEC・文豪ワープロを購入し、夫婦で猛勉強しましたね。もちろん会社や自己の釣り新聞発行でもワープロをフル活用し、数年後やっと会社でもハイレベルなワープロプリンターが導入され、時代の変革をとらえることができました。そして、ワープロからパソコンに移り変わる平成に入ってゆきます。
この時代を先走りする私のアクションは、誰でもやれる事をしていたのでは面白くない!! 私の気迫が、この時代にはありましたね。20代から30代を突っ走った時代には、それをサポートしてくれた釣りキチの先輩、師匠がいました。 つづく